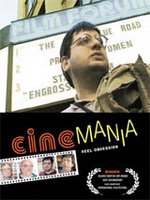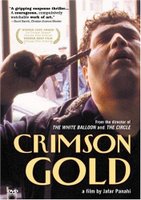Bad Guy:journal
 KIM Ki duk監督の『悪い男』を観た。
KIM Ki duk監督の『悪い男』を観た。やくざもののハンギはある日公園で清楚な大学生ソナに目を奪われる。ソナを見つめるハンギだが、すぐにソナの彼氏が駆け寄ってきてソナには彼氏がいることを知る。しかし、ハンギはおかまいなしに強引にソナに口づけをする。それがもとでトラブルとなり、ソナにののしられてしまう。その後、ハンギはソナを陥れて借金を負わせ、自分が仕切る売春宿に売ってしまう。それはソナへの復讐と彼女を近くでみていたいという屈折した感情からだった・・・。
あまりに激しく、異常なストーリーでちょっとついて行けない感じになるが、監督は歪んだ愛を純愛物語に昇華したかったようだ。しかし、心理学に少しでも通じている人がみれば、主人公の女性は典型的なストックホルム症候群にかかっていることがわかるだろう。この売春宿は構造的には監禁部屋とほぼ同じ状況なので、監禁された女性が過度に男性に好感情を抱くということも理解できる。しかし、多くの観客は、特に男性はこの物語を不器用で純粋な男性の女性への愛が、彼女にも通じたというロマンティックな空想をするに違いない。監督はこうした点に関して鈍感なのか敏感なのかは僕にはわからない。ただ、男性によって都合がよすぎるストーリーだなと呆れるばかりである。これと非常に似た作品はビンセント・ギャロの『バッファロー'66』である。これも男によって連れ去られた女性が最後には男に恋愛に似た感情を抱く物語。KIM Ki dukとヴィンセント・ギャロという一見、系統やスタイルが全く違う監督に共通するのは彼らの「男性性」であろう。彼らはどんな非道い自分でも、どこかに自分を受け入れてくれる女性がいるに違いないというストーリーを好む傾向が強い。僕的にはこんなのはファンタジー以外の何物でもないと思うのだが・・・。