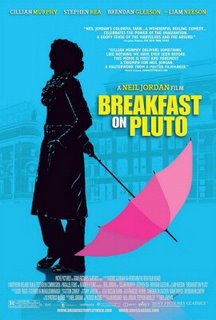C'est vraie, l'enquête?:journal
やや旧聞に属するが、「恋人いる女性は32%、男性24% 「結婚したい」9割」というニュースが朝日新聞のサイトに掲載されていた。これは「調査は05年6月、全国の18歳以上50歳未満で、結婚経験のない独身者約1万2000人を対象にし、8734人の回答を得た。サンプル数が確保できた18〜34歳について集計、分析した」そうだが、未婚同士の男女を扱った統計なら、「恋人がいる」のパーセンテージが8%も食い違うというのはどういうことなのだろうか?
ここで疑問に思うのは「恋人」の定義である。この調査で「恋人」をどう定義したのかは記事からは判らない。ひょっとして、女性は相手を「恋人」と思っているが、男性は「恋人」とは思っていないということもあるのかもしれない。また、女性は相手が既婚の場合も「恋人」としてカウントしているかも知れない。複数の恋人がいる人に二股や三股をかけられている人もいるかもしれない。やや杜撰な印象を受けるこうした社会調査は結論として「結婚願望は強いのに、実際に恋人がいる人は少なく、未婚化や出生率低下の一因」としている。結果ありきの統計「解釈」に思えて仕方ないのは僕だけだろうか?あと、調査では35歳以上の独身者が「分析対象外」になっている。これには何の注釈もないが、ここで切る理由は何なのだろう?
ここで疑問に思うのは「恋人」の定義である。この調査で「恋人」をどう定義したのかは記事からは判らない。ひょっとして、女性は相手を「恋人」と思っているが、男性は「恋人」とは思っていないということもあるのかもしれない。また、女性は相手が既婚の場合も「恋人」としてカウントしているかも知れない。複数の恋人がいる人に二股や三股をかけられている人もいるかもしれない。やや杜撰な印象を受けるこうした社会調査は結論として「結婚願望は強いのに、実際に恋人がいる人は少なく、未婚化や出生率低下の一因」としている。結果ありきの統計「解釈」に思えて仕方ないのは僕だけだろうか?あと、調査では35歳以上の独身者が「分析対象外」になっている。これには何の注釈もないが、ここで切る理由は何なのだろう?