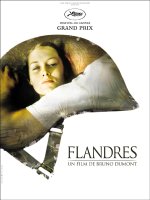late show de Nagoya:journal
夜は退屈なので、映画を見に行くことに。名古屋の映画サイトをみると、夜8時以降のレイトショーは通常1800円が1300円とあり、これでも沖縄より200円高いが暇つぶしに見に行くことに。そして同じサイトで上映時間を確認すると、何と!夜8時以降のスケジュールは組まれておらず、7時30分とか7時40分とかレイトショーの時間帯に食い込まないようになっている。そして劇場に電話で確認すると、レイトショーの時間帯に組まれてない作品はレイトショーの金額が適用されないとの由。つまり、レイトショーで観られる作品は一本もないのだ!
対応した職員の声のトーンからは、良心の呵責などは伝わってこない。このいけしゃーしゃーとした返事に、名古屋に何となく魅力を感じない人が多い理由の一端をみたようだった。因みにこの街にはレディース・デイはあるが、メンズ・デイはない。割引を適用させても1600円を下らない状況を考えると桜坂劇場、パレット市民劇場を擁する那覇市の映画環境は地方都市としては極めて良質であると感じた。