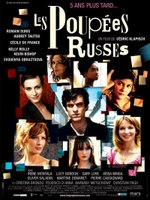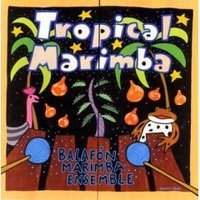Mademoiselle:films
 Philippe Lioret監督のMademoiselleを観た。
Philippe Lioret監督のMademoiselleを観た。一番好きな女優は誰かと訊かれればいつもSandrine Bonnaireを挙げる。しかし日本で彼女の名前を挙げても殆ど誰も知らない。儚いような、少し影のあるような、しかし落ち着いた佇まいが大人の女性を感じさせる。演技も自然でバランスのとれた女優である。この作品はそんな彼女の魅力が静かに光る一本だ。製薬会社の営業をする既婚で子供もいる女性が即興劇団の俳優と短い恋愛をするものだが、劇的すぎない物語の運び方や過剰になりすぎない台詞回しが好感がもてる作品。日常のできごとをそっと切り取って余韻を残すような、ほのかな味わいがある。劇中の「灯台守の物語」のモチーフが形を変えてL'equipier(『灯台守の恋』)に繋がっていく。Bonnaireは出演していなかったが、ParisでLioretの最新作"Je vais bien, ne t'en fais pas."を観たが、この作品も素晴らしかった。Lioretは女優の起用が絶妙である。難しすぎず、かつ良質な大人向けのフランス映画を観たい方は是非、どうぞ。